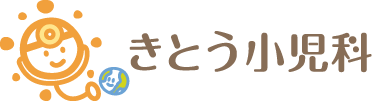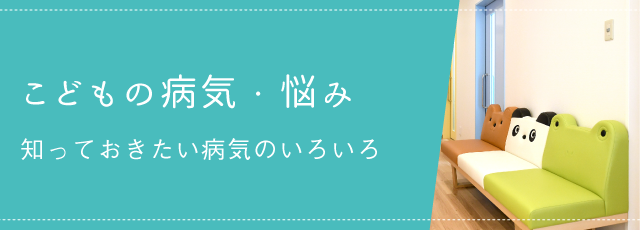起立性調節障害
■起立性調節障害とは
起立性調節障害は、立ち上がったときに血圧や心拍がうまく調節されず、頭がふらつくなどの症状が現れる状態です。主に思春期前後のお子さまや思春期のお子さまにみられ、生活習慣やストレス、睡眠不足なども複数の要因が重なり症状が現れます。朝起きられない、立ち上がるとふらつくなどがあればまずは小児科へご相談ください。
■起立性調節障害の原因
起立性調節障害の原因はさまざまです。
主な原因と体への影響は以下の通りです。
・自律神経の乱れ:立ち上がったときの血圧・心拍の調整がうまくいかなくなる
・水分・塩分不足:脱水状態や低血圧の悪化を招く
・生活リズムの乱れ:体の回復力の低下
・運動不足:筋力と自律神経機能が低下し血流の循環が悪化させる
・心身のストレス:自律神経へ影響を与える
複数の原因が組み合わさって起立性調節障害として現れることが多く、診察ではまずは普段の様子などを詳しく確認します。
■起立性調節障害の主な症状
・立っていると気持ちが悪くなる、ふらついたり倒れたりする
・立ちくらみ、めまいを起こしやすい
・倦怠感、体が重く感じる、疲れやすい
・朝なかなか起きられず、午前中は特に症状が重い
頭痛や吐き気、息切れが現れることもあります。
症状は人により強さや現れ方が異なりますが、朝起きたときに症状が顕著であることが特徴です。
■起立性調節障害の治療
起立性調節障害の治療は、まずは起立性調節障害について知ることから始め、生活習慣の改善を進めていきます。場合によって薬物療法を行うこともあります。
<生活習慣の改善>
・水分、塩分の適切な補給
脱水を避けるため、こまめな水分摂取と適度な塩分摂取を指導します。
塩分は1日10グラム、水分は1日1.5リットルを目安に摂るようにしましょう。
・睡眠の質とリズムの改善
早寝早起きを心掛け規則的な睡眠時間の確保をめざします。
就寝時間が遅い場合は30分ずつ早めていきます。
・適度な運動
無理のない範囲で運動を取り入れ、血流と自律神経の調整を促します。
日中は適度に体を動かし、なるべく横にならないようにしましょう。
・同じ姿勢を続けない
長時間の起立は避け、足をクロスさせて血圧低下を防ぎましょう。
起き上がる時、立ち上がる時は頭を下げてゆっくりと起き上がりましょう。
■お気を付けいただきたいこと
規則正しい生活を送るサポートをしてください。症状が重い場合は朝起きられず学校に行けないこともあります。病状を学校の先生と共有するなどしておきましょう。
また、「朝起きられないのは怠けている」「朝はしんどくて遅刻するのに夜は元気なのはサボりだ」など否定的な発言はお子さまを追い詰め、症状を悪化させる場合があります。ご家族も不安かと思いますが、まずは生活習慣の見直しから始めましょう。
朝なかなか起き上がれない、夕方には元気になるなど一見怠けているように見えますが、実は起立性調節障害かもしれません。
立ちくらみやめまいなどの症状があれば、まずは小児科へご相談ください。